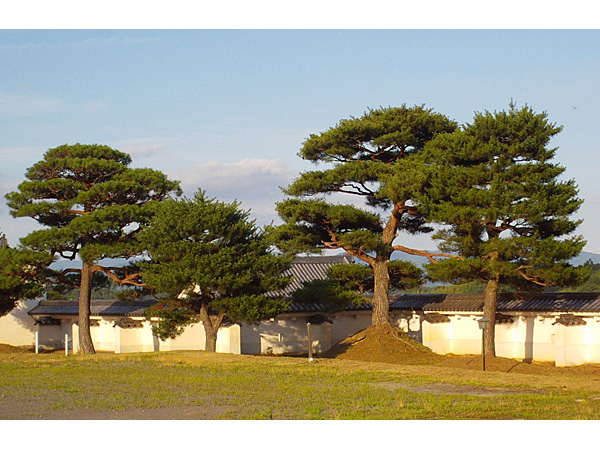松風 第一〇回
謙虚な報道
―日本にジャーナリズムはあるのか―
北野健治
面白い記事が新聞に載っていた。
「日本新聞協会によると2024年の新聞発行部数は約2660万部で、約20年で半減した。(後略)
ネット社会化による地殻変動に既存メディアが順応できず、それゆえに生じる問題を自己言及的に伝える切なさ、ふがいなさ。それが書きにくい理由である。あなたたち自身のせいでしょ、と言われている気がする。実際に言われたことはないけれど。」(「メディア空間考 自分たちのせい? でも、つなぐしか」、朝日新聞、二〇二五年五月二〇日、朝刊、傍点筆者)
私は、雑誌の編集者時代、取材が怖かった。それは、単純に取材がうまくいくか、という不安だけではない。それ以上に感じていたのは、取材者に出会うことによって、生き方を変えなければならなくなるかもしれない、という恐怖だ。
誰かに何かを伝える。公的なメディアなら、心情を交えずに客観的に書くのが基本だろう。が、やはり書き手は人間。どうしても主観的なバイアスがかかるのは認めざるを得ない。
問題は、ここからだ。伝える内容に主観が混じる。では、その伝え手は、取材者から何の影響も受けないで済むものなのか、ということ。
今、考え直せば、プロなら取材者の影響など関係なく、毎回ニュートラルな立ち位置で、その都度異なる取材者に対応できるのかも。
果たして自分の場合は、それはできなかった。記事を伝える以上、その内容に対して少なくともひとりの同時代の人間として受け止めざるを得ない、と考えたわけ。
と、殊勝なことを書いているが、取材対象者全員を全面に受け止めたか、というとエクスキューズせざるを得ない。でも、じわじわと私の精神的内部を蝕んでいたのは事実。まるで進行性の病のように。
「新聞・テレビが『オールドメディア』と呼ばれ、記者志望者が減っても、報道の使命を誰が担うのかという問題は残る。もっとジャーナリズムを支える基本的な条件を意識し、その仕事自体の魅力を伝える工夫が必要ではないか」(「立ち返る ジャーナリズムの原点」、朝日新聞、二〇二五年五月二一日、夕刊、傍点筆者)
時折、思い出したかのように、共同運営者のK.I.(樹)と「日本にジャーナリズムはあるのか」ということが話題に上る。
二人の意見は、ともに「否」。
主張の内容は異なるが、私自身は、「個」が確立していない土壌では、「公」の立ち位置から報道する「ジャーナリズム」は成立しないという考えから。
島育ちの私は、大学生になって島を離れるまでは、家が契約していた読売新聞を読んでいた。当時も今も朝刊のみだ。大学生になってから、保守色が強いと言われていた読売から、リベラルだという朝日新聞の朝・夕刊を購読するようになった。それは、今でも続いている。
今では、読売も朝日も、その姿勢はあまり変わらないような気がする。その最たることは、自分たちは「正義」を報道しているという臭いが、ふんぷんとしているところ。これは両社に限ったことではない。日本のメディアには、「畏れ」を感じない。それが色濃くにじみ出ているのが新聞だ。
「生活者目線」でという記事の視点も、裏を返せば、その立ち位置に合わせてやる、という上から目線を感じる。それが新聞が衰退している原因のひとつと考えられないだろうか。
「謙虚さ」。それはすでに死語かもしれない。言葉を変えれば、「畏れ」。どちらの言葉でもいい。そうした姿勢で貫かれたジャーナリズムの新聞報道を読んでみたい。
2025年5月25日
(つづく)