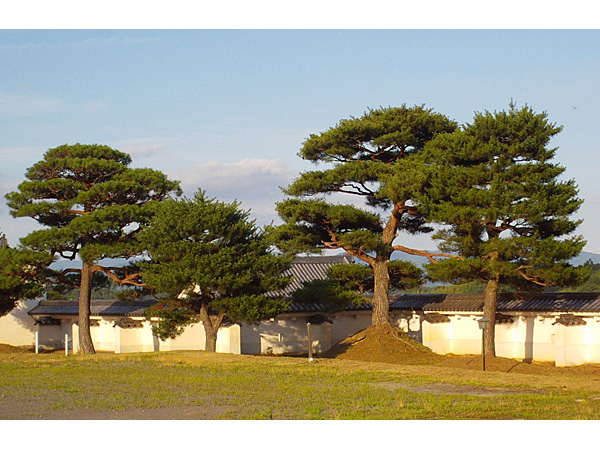松風 第六回
「在る」ことの奇跡―皺の記憶―
Japanese Modern Classic 2
北野健治
ダンスが好きだ。なぜ好きになったのかは定かではない。ただ、ひとつ覚えがある。故郷の島の図書館で、高校生のときに出会った一冊のジャーナルの記事。
いつもの学校帰り、町立図書館に寄る。定期刊行物の棚から偶然手に取ったアサヒグラフに、その人は載っていた。大野一雄。今、ネットで調べると、一九八〇年の第一四回ナンシー国際演劇祭に招聘され、「ラ・アルヘンチーナ頌(以下、「頌」)を舞ったときの記事のよう。
全身白塗りの女装のその人が墓地で舞っている。「」。息をのむほど美しい。それは、一七年間生きてきて経験したことのない「美」だった。心が震える、を通り越して、存在が、魂が揺さぶられるのを実感した。
いつか、きっと、このひとと会わなければいけない――。何の根拠も、手立てもない、島の高校生は確信した。
それから十数年後、出版社に入った私は、その時を得た。取材で訪問したご自宅でのそのひとは、あのときのままだった。
取材を通して印象に残っているのは、一八世紀の北欧の神秘思想家・スウェーデンボルグのことを熱心に語っていた姿。氏はスウェーデンボルグを通して、この世を超えた「愛」そのもののことを語っていたように思う。
取材後に、初めて舞台に接した。それは、ありきたりな「感動」という言葉では表現できないものだった。数回の公演ののち、ついに「頌」を観る。
大野氏の舞踏を通して、いつも観ていたのは、踊りのかたちではなく、踊ることによって顕われてくる魂のかたちだった。それは、「在る」ことに直に触れる経験。
「頌」の公演のとき、どうしても一緒に氏の舞踏に触れたかった友人と観た。舞台が終わったとき、彼女に言った。
「泣くかと思った」
「泣いていたわよ。ワカンなかった? バカ」
彼女は、表情には出さず、泣いていたのだ。
年を経るごとに、体力の衰えは隠しようもなく、白塗りの身体の皺も深く増えていく。
あるとき、日吉の慶応大学の講堂で公演があった。公演後、挨拶をするために、楽屋を訪れた。楽屋というよりも物置に近いそのスペースに、氏はいた。ひとり淡々と白塗りを落とし、着替える氏。そこには垂れ下がる無数の皺を纏った老いた肉体があり、それに余りある精神を観た。
皺。氏の身体の、そのひとつ一つが陰影に富み美しい。なぜなら皺のすべてに、いのちの記憶が刻まれているから。それが舞う姿は、いのちの乱舞だ。
「いのち」も「美」も似ている。どちらも、善悪を超えているから。ただ「在る」ことの奇跡。私はいつも氏を通して、いのち=美の乱舞を経験していた。
氏の亡き後、その乱舞は令息・大野慶人氏が、父とは違ったスタイルで引き継いでいく。
2025年5月10日
(この項つづく)