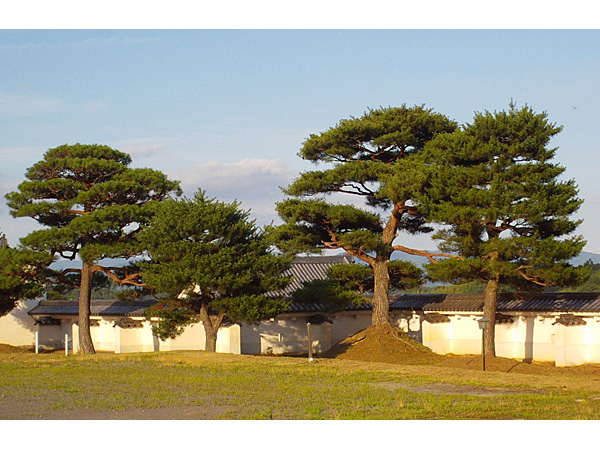松風 第八回
いのちをみせる Japanese Modern Classic 3
北野健治
昭和五〇年代のこの国の情報源は、今に比べると極めて少ない。ましてや、私の故郷の離島になると言わずもがな。というわけで、今回の登場人物を知るきっかけは、シリーズ前回にも触れたアサヒグラフ。
図書館に寄ったときの習慣で、アサヒグラフを手に取る。パラパラとめくっていったあるページで手が止まり、息をのむ。そこには、それまで目にしたことのない植物をモチーフにした“かたち”があった。
不定形なガラス器に、花びらだけをぎゅうぎゅう詰めに押し込み、紙の上に器の口元を下に逆さに置かれた作品。その口元からは、赤いまるで血のような花液が染み出し、滲みながら文様を描く。まるでロールシャッハテストのシミのよう。
その衝撃は、それに続くオーラを放つ各々の作品が掲載された最後のページまで続く。教科書的な乏しい知識で知っていた「いけばな」と言われるものの綺麗さとは違い、グロテスクさも含めて――そう一般的な美醜の概念を超えた「いのち」のかたちが繰り広げられている。
いけばな作家・中川幸夫。彼の名前を鮮明に覚えた一瞬だった。私がショックを受けたいけばな作品たちは、一九七八年にライプツィヒの「世界で最も美しい本」国際コンクールで入賞した『華』に掲載されたものの一部。
それから十数年後、いけばな草月流の機関誌を発行する出版社に入社した私は、氏と会える機会を持つ。会いたい人がための企画ばかり編集会議でプレゼンしていた当時の私。自ずとその一人に中川氏がいた。
三歳のときに脊椎カリエスを患い、身体的なハンディキャップを負った中川氏。氏は、そのハンディを逆手に、生きるエネルギーに換えて作家活動を行う。
彼の生涯の前半は、彼をモデルにした人物が登場する早坂暁の小説『華日記』に描かれている。今でも、いけばな界は基本的には家元制度の中で活動する。そのルールを一九五〇年代に破り、ひとりの作家として「はな」をモチーフに、生涯「いのち」をいけ続けた。
個人的に惜しむらくは、晩年である。本人の意思とは関係なく、マスコミが彼の存在に目をつけ、利用し始めた。それは、シリーズ前回の大野一雄氏も同じこと。マスコミが恐ろしいのは、凄まじい勢いでスポットを当てた対象を消費する装置だから。
まだ一般的にはメジャーではなかった、なる前の中川氏への取材は、それ以降の私の生き方の指針となる。「見ることからすべてがはじまる」。取材記事のタイトルだ。
取材以降、何度か氏の個展に行った。行けば必ず心が動かされる。が、なぜか島で受けた衝撃を上回ることはなかった。それは、ひとえに私自身の問題だと思うのだが……。
最晩年、中川氏は地方のアートトリエンナーレで大野氏とコラボレーションを行う。氏がヘリコプターに乗り上空から約一〇〇万枚のチューリップの花びらを散華する。その降りしきる花弁の中、地上で大野氏が舞う作品。テレビでも特集が組まれ、話題となった。
「こういうことを二人は、本当にしたかったのかなぁ」
先に挙げた小説でも触れられているが、香川県丸亀市の出身の中川氏は、上京して文字通りの赤貧の生活を中野のアパートで始める。それは、私の知る限り東京を去るまで続いていた。
気づくと中川氏に対するマスコミの熱狂が薄れていく。年老いた氏は、華々しい活動ののち、話題になることもなく人知れず故郷に戻っていく。そして、いけばなに生命をかけた人生を終える。
いのちをみせる―見せる―魅せる。今も渋谷の雑居ビルの2階の喫茶店で、口角に泡を溜め、熱く語る氏の姿が彷彿とする。そして思い出す。「見ることからすべてが始まる」。
2025年5月20日
(つづく)