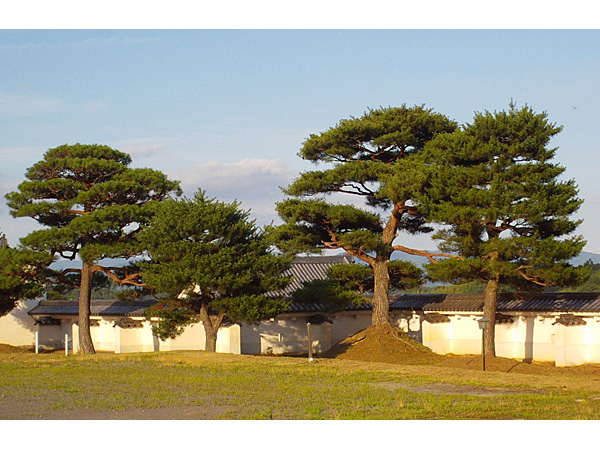松風 第九回
「税」というポピュリズム②
―内部留保税という提案―
北野健治
先日、近所の立ち飲みビストロで、店主のマダムとよもやま話をした。その中で、いつからこの国では格差を感じるようになったのだろうか、という話題になった。昭和の時代には、「一億総中流」の感覚を大半のひとは持っていたよね、という確認も含めて。
個人的には、小泉内閣時代の「構造改革」の一環として行われた労働派遣法の規制緩和がターニングポイントだったような気がする。それまでは、正社員が雇用形態のメインだったのが、非正規雇用が拡大されたこと。
確かに現在の社会情勢では、その影響により労働市場が流動化している。また本来の目論見通り、雇用市場も活性化している。転職紹介エージェントの隆盛ぶりが、いみじくもそれを示している(※ここまで書いてきて気づいたことがある。それは、「ヒト」も市場で取引される「モノ」化しているのではないかということ。これについては、後日回を改めて考えたい)。
シリーズ前回では、消費税減税に対する国会の動きを取り上げた。その後の報道を見ていて、今回は意外と与党の自民党が、安易な減税は反対の意向を示し、政権担当能力を培ってきただけの反応を示している。
消費税は、社会保障費の財源であり、むやみに減税することは、現在の社会保障制度に支障をきたすだけでなく、将来の世代に負担のツケを回すとの判断から。
一方の野党は、「何の対策もしないのか」、と自民党の姿勢を批判するのみ。減税に対する対案を今のところ目にした記憶はない。
従来の制度で、納税額金が増えるということは、短絡的に考えれば景気が良くなるということ。つまりお金が回ればいいわけだ。一番身近な例で考えれば、みんなの使えるお金が増えること。生活と将来の不安がなくなれば、むやみに節約に走ることもなく、貯蓄はするだろうが、今よりはお金が市場に回るのではないか。
毎年、春闘でベースアップが話題になる。問題は、パーセンテージではない。被雇用者に、正当な労働対価としての報酬が支払われているかどうか。
さて、ここからが経済アナリストでもないアマチュアの提案。リーマンショック以降、私感として企業の内部留保率が高まったような気がする。社員が奮起して利益を上げても、それが社員に還元されていないのでは。
そこで、企業規模に応じて、内部留保率の上限を設定するのはどうか。と同時に、内部留保率に応じて、規定以上の場合は新しい法人税率を負荷する。名付けて「内部留保税」。
個人所得もだが、この際に雇用関係を見直しするのもありかも。今、浸透しつつあるジョブ型雇用をはじめ、先の非正規雇用の形態が、果たしてこの国の風土に合っているのかを検証してみる必要性がある。
いつも思うのだが、誰しもが新人のときがあるわけ。現在の転職風潮を見ていると、雇用者も被雇用者も、「誰がひとを育てるのか」、という視点が欠けている。
法も制度も生き物だ、その時代に合ったものが生まれ、合わなくなったものは見直すべきだ。「一億総中流」がいいとは言わないが、少なくともこの国に生きているみんなの「全生活者安心感」が得られるように。
2025年5月23日
(つづく)